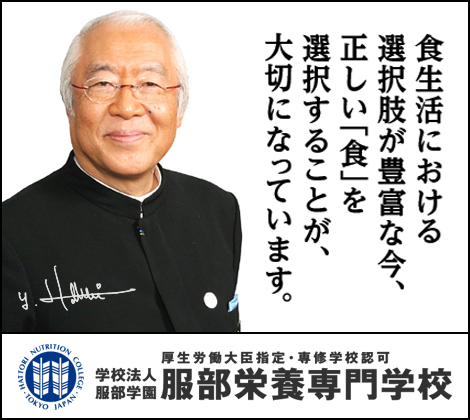寒天ゼリーや水ようかんなど、和菓子作りでよく使われている寒天。
今回は寒天の種類や用途に合わせた使い方などのお話です。
【「寒天」はどのようにして誕生したの?】
寒天は原料である「テングサ」や「オゴ草(オゴノリ)」などの海藻類を煮溶かし、凍結乾燥させたものです。
寒天とよく似た「ところてん」は、仏教が伝わった538年ごろに中国から作り方が伝えられたといわれていますが、寒天はそのところてんを保存しているときに偶然誕生した日本オリジナルの食材です。
江戸時代、京都の旅館店主が冬場にところてんを外に出しておいたところ、冬の寒さでところてんが凍り、自然乾燥の状態になりました。
このことから旅館の店主がひらめき、寒天の製法が編み出されたといわれています。
【寒天の種類】
寒天は「角寒天(棒寒天)」や「糸寒天」、「粉寒天」の3種類があります。
「角寒天(棒寒天)」、「糸寒天」は、主にテングサを原料に用い、自然の寒気を利用する伝統製法が主流ですが、テングサの収穫量の減少や原価価格の高騰になどにより、オゴ草を合わせて作られることが多くなっています。
「粉寒天」はオゴ草を主原料とし、凍結させず、脱水・圧縮・乾燥させて粉末状にしています。
【寒天の使い方】
■角寒天
よく洗ってから適当な大きさにちぎり、水に浸してふやかし、水気をしぼってから使います。(30分程度水につけておくと、溶けやすくなります)
そのあと分量の水に入れて火にかけ、かたまりが消えるまで煮ます。
※角寒天1本(約8g)で粉寒天小さじ2(約4g)と同じくらいの凝固力があります。
■糸寒天
よく洗ってから水に浸してふやかし、水気をしぼってから使います。(そのまま使用する場合は5~10分、煮溶かす場合には30分~1時間程度水につける)
煮溶かして使うときは、そのあと分量の水に入れて火にかけ、かたまりが消えるまで煮ます。
※糸寒天8gで粉寒天小さじ2(約4g)と同じくらいの凝固力があります。
■粉寒天
水にふやかす必要はありません。
分量の水などに粉寒天を入れ、よく混ぜてから火にかけます。
沸騰したら中火にし、ダマにならないようかき混ぜながら2分程度加熱して煮溶かします。
【寒天がきれいにかたまらないのはなぜ?】
■しっかり溶かしていなかった
寒天の融点は、90~100℃です。
そのため、鍋の側面が沸々した程度で加熱を終了してしまうと、しっかりと寒天が溶けきらず、きちんとかたまりません。
しっかりと沸騰させ、十分に煮溶かしてから火を止めてください。
■酸味の強いものを一緒に煮た
寒天は酸に弱いという特徴があります。
寒天ゼリーにオレンジジュースやレモン汁を入れることも多いと思いますが、酸味のあるものと寒天を一緒に煮てしまうと、かたまらない原因に。
酸味のあるものは、しっかりと寒天を煮溶かしたあと、火を止めてから加えるようにしてください。
■寒天液に冷たい液体を加えてしまった
寒天は、30~40℃でかたまります。
そのため、寒天液に冷たい液体を合わせると均一にかたまらなかったり、ダマになってしまうことがあります。
あとから加える液体は、人肌程度に温めてから加えてください。
【寒天には食物繊維がたっぷり!】
寒天は100%海藻から出来ており、全体の約80%を占めるほど食物繊維が豊富に含まれています。
食物繊維は、便秘改善や腸内環境を整える働きが期待出来ます。
さらに、腸内で水分を吸収してくれるので満腹感が得られやすくなり、食べ過ぎを防いでくれます。
このほか、血糖値の上昇を抑える働きや余分なコレステロールを体外に排出するのにも役立ちます。
寒天は手軽に食物繊維がとれ、ダイエットにも効果的な食材ですが、それだけ食べていると栄養が偏ってしまいます。
肉や魚などのたんぱく質、ビタミンミネラルが摂れる野菜などと一緒にバランスよく食べましょう。
【寒天とゼラチンの違いとは?】
冷たいデザートを作るとき、寒天とゼラチンのどちらを使うのか迷ってしまうことがありますよね?
どちらも食材をかためる働きを持ちますが、食感や見た目などに違いがあります。
ぜひ、それぞれの特徴を覚え、使うときの参考にしてください。
寒天は歯切れがよく、ツルンとした食感が特徴です。
凝固力がゼラチンよりも強く、加熱したあとは常温でかたまり、一度かたまると常温でも溶けにくい性質を持っています。
溶かすと白く濁った色をしているので、透明感を出したい料理には向いていません。
用途としては、水ようかんや杏仁豆腐などによく使われています。
ゼラチンは口どけがよく、やわらかい食感が特徴です。
弾力と粘性が強く、ゼリーやムース、ババロアなどを作るときによく使われます。
加熱したあとは20℃以下でかたまります。寒天とは違い、常温に置くと溶けてしまうので注意が必要です。
寒天は食材をかためるだけではありません。
糸寒天はサラダやスープ、粉寒天はごはんにほんの少し加えてもおいしいです。
2月16日は「寒天の日」。
ぜひこの機会に、さまざまな料理に寒天をプラスしてみてはいかがでしょうか。
Text by まち/食育インストラクター