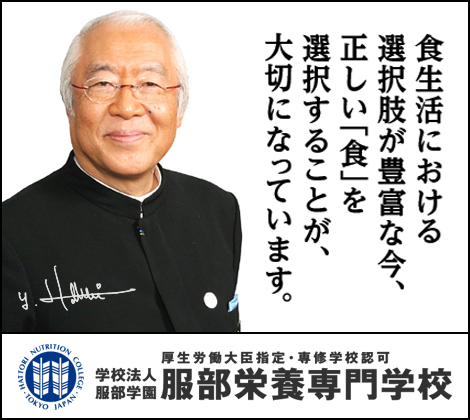福島県中通り北部を発祥とした郷土料理の「いかにんじん」。
昨今ではメディアや商品コラボもあり、知っている方も多いのでは?
今回はそんな「いかにんじん」についてのお話です。
【郷土料理とご当地グルメの違い】
旅行やちょっとしたお出かけの計画中に耳にする「郷土料理」、「ご当地グルメ」といった言葉。
せっかく出かけたのならそこの名物を食べたくなりますが、これらの2つの違いについてご存じですか?
同じようにも感じますが、違いがあるんです。
郷土料理とは、地域の素材を使って作られた、古くからの伝統を伝える料理のことで、その地域に住む人々の家庭料理のようなものです。
一方ご当地グルメとは、町おこしの一環としての役割があり、その地域特有の食材や調理方法で作られた料理のことです。
【福島県の魅力】
まず、いかにんじんのご紹介の前に、発祥の地である福島県についてお話します。
福島県は北海道、岩手県に次いで日本で3番目に広い面積を持つ県で、会津地方・中通り地方・浜通り地方の大きく3つに分けられます。
福島県は縁起のよいデザインや多彩な加飾の美しさが特徴の「会津塗」や赤い牛の張子人形で、首がゆらゆら揺れる郷土玩具の「赤べこ」などが有名です。
「起き上がり小法師」は転んでも起き上がる張子細工で会津地方の民芸品です。
ほかにも、会津若松市にある鶴ヶ城(若松城)は、日本百名城のひとつです。
魅力あふれる福島県に一度は訪れてみたいですよね。
【いかにんじんってどんな料理?】
さて、今回は福島県の郷土料理のなかでも、「いかにんじん」についてお話します。
いかにんじんは、するめいかとにんじんを細長く切りそろえて、しょうゆベースのつけ汁につけ込んだ郷土料理です。
甘じょっぱい味が特徴で、福島県中通り地方北部が発祥です。
いかにんじんの歴史は古く、100年以上前から存在していたといわれています。
北海道の「松前漬け」とよく似ていますが、松前漬けには昆布が入っており、いかにんじんは入っていないという違いがあります。
料理のルーツは定かではなく、松前漬がいかにんじんのルーツなのではないか、海に面していない内陸で新鮮なイカの食感を再現するために開発されたのではないかなど、諸説あります。
また、現在では一般的な惣菜として食べられていますが、もともとは冬の保存食として作られていました。
つけダレに数日つけて出来上がるいかにんじんは長持ちするため、雪が多く冬に作物を収穫しにくい福島で重宝されていたそうです。
また、正月に欠かせない郷土料理としても親しまれています。
【実際にいかにんじんを作ってみよう】
<材料(2人分)> 調理時間:20分
するめいか(干物)・・・1/2枚
にんじん・・・1/2本
A砂糖・・・小さじ2
A酒・・・1カップ
Aしょうゆ・・・大さじ1
<作り方>
- するめいかを縦に3等分してから細く千切りにする。
- にんじんはするめいかと同じくらいの長さにして千切りにする。
- Aを鍋に入れ沸騰させ、冷やす。
- ボウルに(1)・(2)を入れ、(3)を入れてつけ込む。
いかにんじんは、そのまま食べてもおいしいですが、数日間タレにつけ込むことで味が深まります。
地域によっては、仕上げにいりごまを加えるところもあります。
いかがでしたか?
簡単に作れておいしいいかにんじん。
おつまみにもご飯のおかずにもなり、かき揚げや炊き込みご飯などさまざまなアレンジもできます。
ぜひ福島県の味覚をご自宅で味わってみて下さい。
Text by あお/食育インストラクター