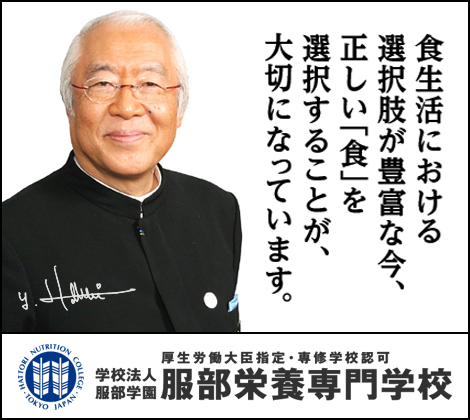暖かくなると、さまざまな木々の新芽が顔を出し、春の訪れを感じます。
このころになるとスーパーなどでたくさんの山菜が並び始めます。
特有の風味が魅力の「山菜」。
今回はよく見かける山菜をいくつかご紹介します。
【古くから親しまれてきた「ふき」】
ふきは、日本や中国、朝鮮半島に分布している数少ない日本原産の野菜です。
平安時代にはすでに栽培されていたと考えられ、古くから日本人に親しまれてきました。
現在多く出回っているのは、根元が赤みがかった「愛知早生ふき」です。
<ふきの下処理方法>
ふきはアクが強いので、調理前にゆでてアク抜きをする必要があります。
まず、茎を鍋に入る長さにカットし、まな板の上に並べて塩をかけ、両手で前後に転がすように板ずりします。
そのあと、塩をつけたままたっぷりの湯で4~5分ゆでて水にとり、冷めたら皮をむけば下処理の完了です。
すぐに使わない場合、水につけて冷蔵庫で保存します。毎日水をかえ、3~4日のうちに使い切るようにしましょう。
【特有のほろ苦さが魅力「ふきのとう」】
ふきのとうは、先にご紹介した「ふき」のつぼみです。
縄文時代から食べられていて、平安時代にはすでに栽培が始まっていたとされています。
独特のほろ苦さとホクっとした食感を持ち、天ぷらや和え物、佃煮、炒め物など幅広く使われています。
<ふきのとうの下処理方法>
ふきのとうは、切るとすぐに黒く変色してしまうほど、アクの強い食材です。
お浸しや和え物を作るときには、アクや強い苦味をある程度ぬく必要があります。
たっぷりの水に塩を加えて2~3分ゆで、しっかりと水にさらしてから料理に使いましょう。
たくさん購入してすぐに食べきらないときは、アク抜きしたものをビニール袋に入れ、冷凍庫で保存することも可能です。
使うときは、そのまま自然解凍させればOKです。
【山菜の王様「たらの芽」】
日本各地の山野に自生するタラノキの若い木の芽で、「山菜の王様」とも言われています。
さっとゆでて和え物にしてもよいですが、油と相性がよいので、天ぷらがおすすめです。
<たらの芽の下処理方法>
たらの芽の根元には、茶色くてかたい三角の形をしたはかまがあります。
これが残っていると口あたりが悪くなるので、取り除いてください。
種類によってはトゲがあるものもありますが、このトゲは加熱するとやわらかくなるので、取り除く必要はありません。
和え物やお浸しにするときにはアク抜きが必要です。
塩を加えた熱湯で2分ほどゆで、冷水にしばらくつけてから使いましょう。
【シャキッとした食感の「うど」】
うどは、全体が白い「軟白うど」と、緑色の「山うど」の2種類に分けられます。
スーパーなどでよく見かけるのは軟白うどで、地下の室(むろ)で日に当てず育てられるため、全体が白くなります。
山うどは本来、山野で自生しているもののことを言いますが、収穫量が少なく、ほとんど流通することがないようです。
そのため、店頭で売られている山うどは、軟化栽培したうどにあとから光を当てて緑色をつけています。
<うどの下処理方法>
うどは穂先から茎、皮まで、ほとんどが食べられる山菜です。
太い茎の部分は皮を厚めにむき、繊維に沿って切ると食感よく仕上がります。
変色しやすいので、カットしたら酢水に5~10分つけてから使いましょう。
穂先部分は天ぷら、茎は和え物、皮はきんぴらがおすすめです。
【特有の苦みには嬉しい効果が!?】
「「春の皿には苦味を盛れ」ということわざを聞いたことがありますか?
この苦味とは、山菜などの春野菜のことを表しています。
山菜の苦味やえぐみは、ポリフェノールという成分によるものです。
強い抗酸化作用を持ち、生活習慣病予防や、血流の改善にも効果が期待できます。
また代謝を活発にして冬の間、体に溜まった脂肪や毒素などの老廃物の排出を助けてくれます。
冬の体から春の体にチェンジするためにも、春野菜がよいとされてきたのですね。
春は冬との気温差などで体に不調がでやすい季節でもあります。
おいしいだけでなく栄養がたっぷりの山菜を、ぜひ普段の食事にとり入れてみてください。
Text by まち/食育インストラクター