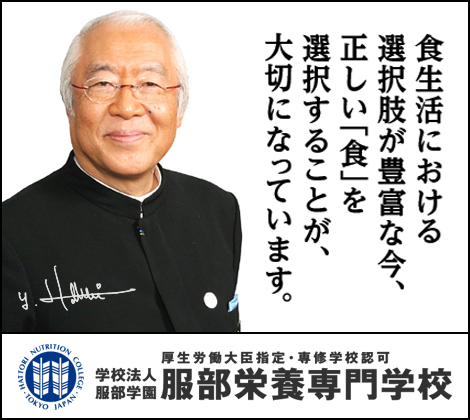日本近海で獲れる代表的な魚のひとつである「カツオ」は一年中食べられる魚です。
季節になると「初鰹」や「戻り鰹」など聞いたことはあっても、よく分からないという方も多いと思います。
今回はそんなカツオについて詳しく解説していきます。
【そもそもカツオってどんなお魚なの?】
カツオは温かい海を好み、群れを成して動き回る魚です。
日本近海のカツオは冬から春にかけて、フィリピン沖付近で産卵します。
卵から孵化した成長途中の魚たちがエサを求めてフィリピン沖を旅立ち、沖縄から九州の南を通って北上していきます。
この時期に漁獲され、千葉県や東北の漁港に水揚げされるカツオを「初鰹」と呼びます。
そして、日本近海でエサを食べてお腹いっぱいになったカツオたちは、秋ごろにまた南の温かい海に戻っていきます。
これが「戻り鰹」です。
【初鰹とは?】
先ほど、南から北上するカツオのことを「初鰹」だとご説明しました。
それは、一年で最初に水揚げが始まるカツオであることからそう呼ばれています。
初鰹は透明感のある赤身でさっぱりとした味わいが特徴です。
引き締まった歯ごたえで、カツオ特有の香りが少ないので、カツオが苦手な方でも食べやすいですよ。
初鰹は縁起物としても有名で、江戸時代の人々に珍重されていました。
しかし当時初鰹は、非常に高価だったため、「まな板に 小判一枚 初鰹」と詠まれていました。
これは、まな板に置いてあるカツオが、あたかも小判が一枚置いてあるように錯覚してしまう。という意味です。
つまり、まな板の上の初鰹は、小判に匹敵する価値があると示しています。
当時の小判一枚の価値は、今でいう数万円~数十万円にもなるんです。
【戻り鰹とは?】
秋ごろにかけて南下を始めるカツオは「戻り鰹」になります。
エサを追い求めて、黒潮とともに北上している途中で獲られる初鰹に比べ、より多くの脂肪を含むため、「トロガツオ」とも呼ばれるほど濃厚な味で、もちっとした食感が特徴です。
秋の味覚として初鰹に負けないほどの人気となっています。
【カツオの栄養】
●DHA(ドコサヘキサエン酸)・EPA(エイコサペンタエン酸)
DHA・EPAは魚に含まれている脂肪酸で、どちらも体内でほとんど作ることができません。
また、DHAには脳を活性化される効果があるといわれています。
EPAは血液をサラサラにする効果があるため、心筋梗塞や脳梗塞などのリスクを減少させます。
●たんぱく質
たんぱく質は筋肉や臓器、皮膚、髪の毛など体の組織を構成したり、ホルモンや酵素、抗体などの体を調節する成分の材料にもなります。
●ビタミンD
ビタミンDはカルシウムの吸収を助けるので、丈夫で強い骨に導きます。
不足すると骨が弱くなり骨粗しょう症の原因になるので注意が必要です。
●ビタミンB12
赤血球の産生や、貧血予防にも効果的なビタミンB12。
血合いに多く含まれているため、残さず食べるのがおすすめです。
【おいしいカツオの選び方】
カツオは非常に鮮度が落ちやすい魚です。
柵や刺身などの切り身で購入されるときは、下記のポイントをおさえましょう。
- 身が鮮やかな赤色
- 血合いが黒くなっていない
- 切り口が虹色に光っていない
- 表面の皮と身の間がピンク色に近い色
また、スーパーなどで購入するときの注意点として、照明の下で選ぶのではなく、手に取って照明の光から外してみるのもポイントです。
いかがでしたか?
初鰹について知っていただけたと思います。
春が来たら初鰹、秋が来たら戻り鰹と季節で味の違いを感じてみるのはいかがでしょうか?
Text by あお/食育インストラクター