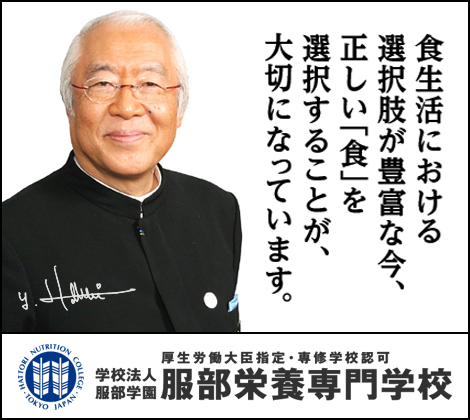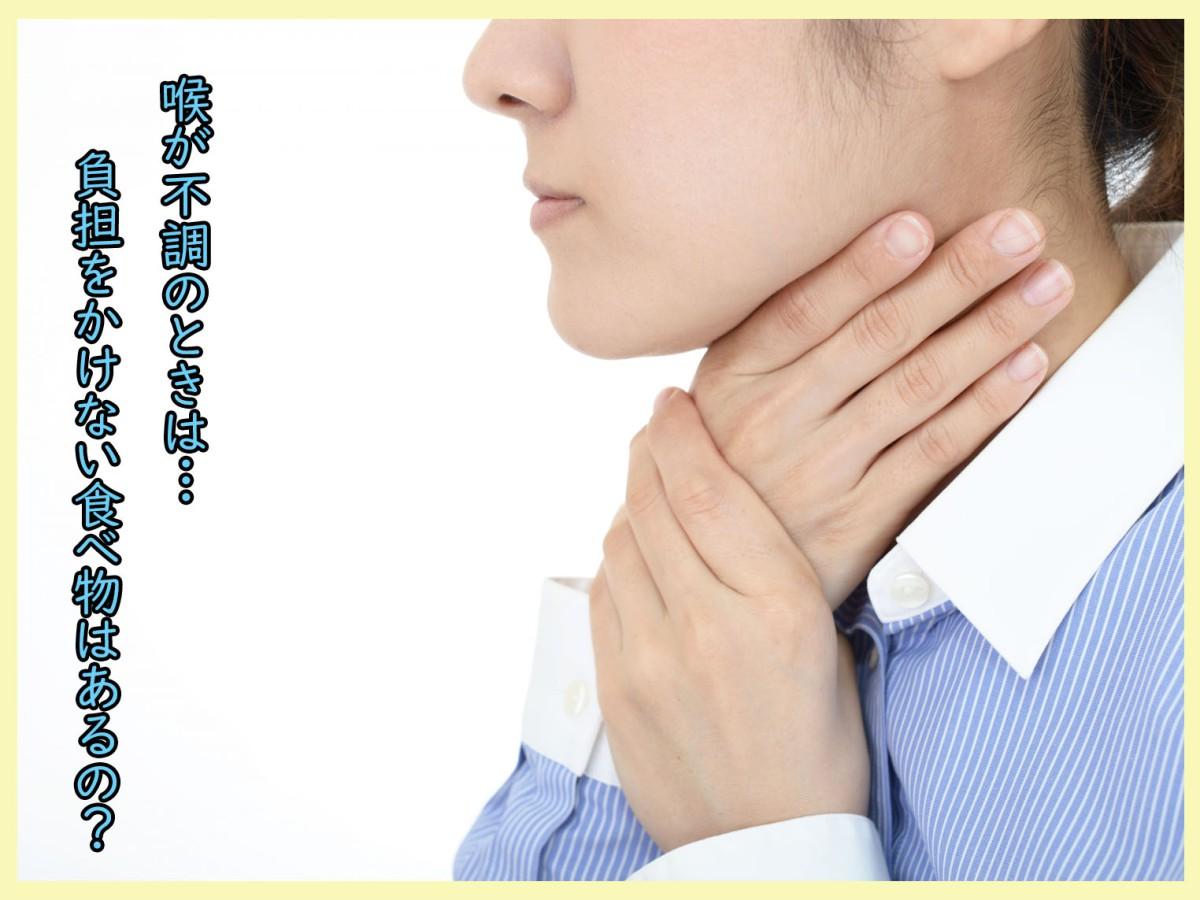
空気が冷たく、乾燥する冬場は喉によくない季節だと言われています。
では、ほかの季節なら大丈夫かというと…?実は、喉を巡る環境はいつも過酷なのです。
今回は喉の調子に関わる食べ物や飲み物についてのお話です。
【喉を巡る環境はいつでも厳しい?】
普段の挨拶から白熱する議論まで…日常生活の中で言葉を話す機会はたくさんあります。
そのため、発声器官である喉は、ごく普通に過ごしていても酷使されている器官です。
さらに、喉は空気の通り道でもあるので、さまざまな病原菌などが侵入しやすく、炎症が起こりやすい部分でもあります。
季節により喉へのダメージの大小は変わりますが、喉のケアについて考えることは、風邪を始めとする感染症の予防にも繋がるので、覚えておくに越したことはありません。
そんな喉に負担をかけていることのひとつに、食事があります。
日々のエネルギー補給が必要なので、ものを食べないわけにはいきませんが、食べ物は喉に直接触れるので、想像以上にダメージを与えている場合があるのです。
「ちょっと喉が痛いな」、「咳が出るかも」…そんな時には、食べ物についてチェックをすることで、悪化を防ぐことができるかもしれません。
【喉に負担をかけないために】
喉に負担をかけやすい食べ物のひとつが、辛い食べ物です。
辛い食べ物は刺激が非常に強く、特に喉が炎症を起こしているときなどに食べると悪化を招く可能性もあります。
辛いものが好きな人でも、体調とよく相談しながら食べるようにしましょう。
ほかには、酸味の強い食べ物も刺激が強く、喉に負担をかけやすいので、食べ過ぎない・体調のよくないときは控える、というようにした方がよい食べものです。
また、飲み物にも注意するべきポイントがあります。
極端に熱い・冷たい食べ物は、喉に強い刺激を与えるので、飲みごろの温度を意識したいところです。
ほかには、アルコール飲料は喉に刺激があるうえ、利尿作用があり脱水や粘膜の乾燥を引き起こし「酒焼け」を起こす原因になります。過度の飲酒は控えましょう。
【喉によい食べ物とは?】
反対に、喉に負担をかけない食べ物とはどんなものがあるでしょう?
ひとつ目は大根です。
大根に含まれる辛み成分のイソチオシアネートは、喉の炎症を抑え、殺菌作用があると言われます。
加熱すると効果が弱まってしまうので、生のままで食べるのが理想的。
そして、すりおろすことで消化・吸収が早まるので、大根おろしとして食べるのが一番効率のよい食べ方です。
ほかに身近な食品では、はちみつがあります。
漢方の考え方では、はちみつは肺を潤し、喉の不調や咳を鎮める効果があるとされています。
また、はちみつには抗菌・抗炎症作用があるため、喉の調子がよくないときにはよい効果が期待できます。(※乳児ボツリヌス症のリスクがあるので、1歳未満の赤ちゃんにはちみつを与えないようにしましょう)
そのほか、嚥下したときに直接喉に触れるので、かたいものや繊維のあるものは避け、のど越しのよい食べ物を優先的に選ぶようにしましょう。
主食であればお粥やうどんなどが適しています。
主菜ならかたい肉などは避け、豆腐や白身魚・卵などのやわらかいものがよいでしょう。
酷使による喉の不調のときは、食べ物に気をつけ、なるべく話さないようにし、適度な休養をとることで改善が早まります。
一方、風邪などの感染症が原因の場合は、すでに体内に入り込まれている状態なので、食べ物だけで治そうとせず、医療機関を受診するなどの必要があります。
ご自身の体調を見極めながら、喉をいたわって下さいませ。
Text by はむこ/食育インストラクター