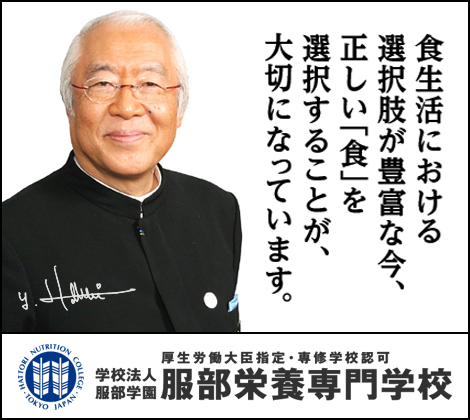シャキシャキとした食感が魅力の「水菜」は今がおいしい季節です。
今回は「水菜」のうれしい効能と簡単レシピをご紹介します。
【水菜とは?】
京都原産の野菜で「京菜」とも呼ばれています。
1年中出回っていますが、冬から春にかけて旬を迎える野菜です。
シャキシャキとした食感とクセのない味が特徴で、サラダなどの生食はもちろん、鍋料理に入れたり、炒め物にしたりとどんな料理とも相性抜群です。
主な生産地は茨城県で、全体の約50%が栽培されています。
そのほか、福岡県や京都府、埼玉県でも多く作られています。
【水菜を長持ちさせるには?】
選ぶときは、葉が鮮やかな緑色で、葉先がピンとしているものを選びましょう。
また、茎が白く曲がってないものが良品です。
水で濡らしてかたくしぼったキッチンペーパーで包み、ビニール袋に入れて冷蔵庫の野菜室に入れて保存します。
このとき、可能であれば立てて入れると、よい状態が長持ちします。
それでも2~3日のうちには使い切るようにしてください。
食べきれないときはゆでて冷凍保存もできますが、シャキシャキとした食感は失われてしまうので注意が必要です。
【「水菜」に含まれる栄養素と嬉しい効果】
水菜は90%以上が水分ですが、β-カロテン・ビタミンC・ビタミンEなどのビタミンが多く含まれています。
「β-カロテン」は皮膚や粘膜の健康をサポートし、免疫力を高めるほか、抗酸化作用により、老化やがんの予防に効果が期待できます。
「ビタミンC」はコラーゲンの合成に関わり、骨や皮膚、血管の維持に欠かせない栄養素です。
また、シミやくすみの原因であるメラニン色素を減らす働きがあり、美肌づくりに役立ちます。
「ビタミンE」は強い抗酸化作用があり、老化や動脈硬化などの予防に役立ちます。
さらに血行をよくする働きがあり、肩こりや冷え性の改善にも効果が期待できます。
ビタミンだけでなく、高血圧予防やむくみの改善に働く「カリウム」、骨や歯を丈夫にする「カルシウム」、貧血の予防に役立つ「鉄」などのミネラルも含まれます。
【栄養を無駄なくとり入れるには?】
■ビタミンCを効果的にとるには…
ビタミンCは、水溶性ビタミンなので、水に溶けやすいという性質を持ちます。
栄養効果を期待したいのであれば、ゆでるより、生のままサラダなどにして食べるのがおすすめです。
ただし、切った水菜を水にさらすとビタミンCが流出してしまうので、切る前にしっかり洗い、切ったあとは水にさらさず、そのまま食べましょう。
また、スープなど、煮汁ごと食べられる料理にすれば、溶け出したビタミンもとることができます。
■β-カロテン、ビタミンEを効果的にとるには…
β-カロテンやビタミンEは脂溶性のビタミンです。
脂溶性ビタミンは、水に溶けにくく、油に溶けやすい性質を持つので、油脂と一緒にとるのがおすすめです。
お肉と一緒に食べたり、油でサッと炒めると吸収率がアップします。
【水菜がたくさん食べられる!「豚肉のハリハリ鍋」】
ハリハリ鍋とは、水菜と鯨肉をつかった鍋料理で、大阪府の郷土料理としても知られています。
現在では、鯨肉がなかなか手に入らないため、豚肉などで代用することが多いようです。
「ハリハリ」は、水菜を食べたときのシャキシャキとした食感から名づけられたといわれています。

<材料(2人分)> 料理時間:20分
豚バラ肉(しゃぶしゃぶ用)・・100g
油揚げ・・1枚
水菜・・2株
A出汁・・3カップ
A酒・・大さじ1
Aみりん・・・大さじ1
A薄口しょうゆ・・大さじ1
<作り方>
- 油揚げは2cm幅に切る。水菜は4~5等分に切る。
- 鍋に湯を沸かし、豚肉を入れて火を止める。菜箸でほぐしながらゆで、色が変わったら取り出す。
- 土鍋(または鍋)にA・油揚げを入れて火にかけ、沸いたら豚肉を加える。
水菜を加えてサッと火を通し、火を止める。
水菜は食べる分ずつ火を通したほうが、シャキシャキの食感が楽しめます。
お好みでゆずをしぼったり、七味唐辛子をかけてもおいしいです。
鍋料理にするとカサも減り、水菜がたくさん食べられます。
サラダや漬物、和え物などはもちろん、煮ても炒めてもおいしい水菜。
ぜひ、今がおいしい水菜をいろいろな料理で味わってください。
Text by まち/食育インストラクター