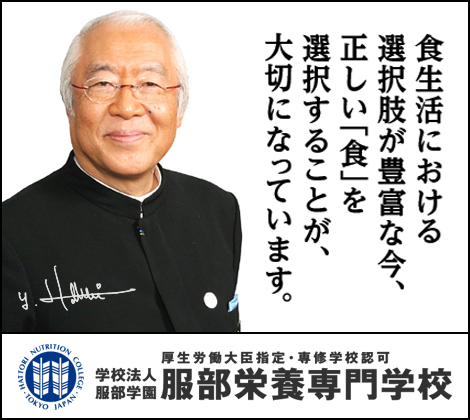1歳半ころを目安に離乳食期が完了し、幼児食へと移行します。
今回は、幼児食とは何か、そして作る際のポイントなどをご紹介します。
【幼児食とは】
幼児食は、離乳食が完了した子どもが次に進むステップで、離乳食が完了する1歳6カ月くらい~小学校入学前の5歳ころの子どもがあてはまります。
離乳食が完了したからといって、すぐに大人と同じ味つけやかたさなどを食べることが出来るようになるわけではありません。
離乳食で歯や歯ぐき、舌を使った食べ方を学びましたが、まだ完全とは言えません。
大人と同じような食事のかたさが食べられるのは6歳以降とされていますが、塩分に関しては12歳ころまでは大人より薄味が望ましいです。
【役割】
先ほども書きましたが、幼児食は大人の食事を食べられるようになるための時期です。
離乳食期は、なんとなく自分で食べられる…ようなところまで成長していきますが、基本的には大人の介助があって成立しています。
幼児食では、自立して食事を摂れるようになることも重要なポイントです。
役割としては、
- よく噛んで食べることを身につける
- 味覚を育てる
- 薄味に慣れさせ生活習慣病になりにくい体作りを目指す
- 朝ごはんを食べる習慣をつけ、生活リズムを整える
- 自分で食べられるようにする
- 買い物などを通して食材に触れ、食への関心を高める
- 「いただきます」、「ごちそうさま」の習慣をつける
などが挙げられます。
これらは、食育の一環でもあります。
体や心がどんどん成長するこの時期に、食育も一緒に始めていくと、食に対するさまざまな知識やマナーが身につきます。
【離乳食からの切り替えのタイミング】
幼児食への切り替えのタイミングは、
- 離乳食完了期ころの目安とされる「やわらかめの肉団子」くらいのかたさのものを、奥の歯茎などで噛める
- 栄養のほとんどを食事や補食から摂れ、食事を楽しめている
などが見られれば、少しずつ始めていきます。
好きな食材や食べやすそうな食材は大きめに切ったり、今までより少しかために仕上げたりして様子を見ます。
食べにくそうであれば、かたさだけ前段階に戻したりするなど、離乳食期と同様に、行きつ戻りつしながら進めてください。
このころの成長は個人差が大きいので、離乳食完了期くらいから徐々に幼児食に移行する子もいれば、完了期を過ぎてしばらくしてもまだ咀しゃく力的に難しい子もいます。
同じくらいの月齢の子が、自分の子どもよりも先に進んだからといって、焦ってはいけません。
自分の子どもとしっかりと向き合い、日ごろの食事の様子を観察しながら進めましょう。
また、食事量も個人差が大きくなりますし、好き嫌いや食べムラなども増えるかもしれません。
身長の伸びや体重の増加などにも目を向け、気になる場合は小児科医や地域の栄養士などに相談してみてください。
【誤嚥に注意】
段々と大人の手を借りなくても食べられるようになる半面、まだまだ遊び食べなども多いころです。
またおしゃべりも上手になってくるので、食べながらお話ししてしまう子も少なくありません。
幼児期の咀しゃく力は、5歳前後でもまだ大人の7割程度しかないので、思っていたよりも大きな塊が喉の方に落ちてしまうころもあります。誤って気管に入ってしまった際も、咳をして口の中に戻そうとする力が弱いので、上手くいかない場合もあります。
何かをしながらの「ながら食事」は誤嚥に繋がりやすいので、「食事に集中出来る環境を整える」・「お口の中にものが入っている時はお話はやめようね」などの声掛けをしていきましょう。
かたさのほか、丸みのある食材や食べにくそうなものは食べやすい大きさに切る、弾力や粘性のある食材を出すときはいつも以上に「しっかり噛む」ことを教えるなどしてください。
幼児食は1歳6カ月ころ~5歳ころまでと実に幅広いので、ある程度自分で食べられるようになってきても、食事の際の見守りは続けましょう。
【引き続き気を付けたい食物アレルギー】
幼児食期になると、多様な食材を食べられるようになっているので、食べたことがない食材に対して、大人の方でもついうっかりということも増えていきます。
体も段々と強くなっているので、離乳食期にはダメだった食材も幼児食期の年代で食べられるようになるケースも多いです。
しかし、ナッツ類や魚卵・甲殻類・南国のフルーツなどは離乳食期にはあまり食べさせないパターンも多く、幼児期に初めて食べてアレルギーを発症することがあります。
比較的軽症な場合、気がつかないこともありますが、重篤になると生命の危険をともなうこともあるのが食物アレルギーです。
食べさせたことがあるか迷った時は、少量で様子を見ましょう。
離乳食期の大変さとはまたちょっと違うのが幼児食ですが、楽しく食事をするということは引き続き変わりませんので、食べることが好きになってくれるように工夫してみてください。
Text by さゆり/食育インストラクター