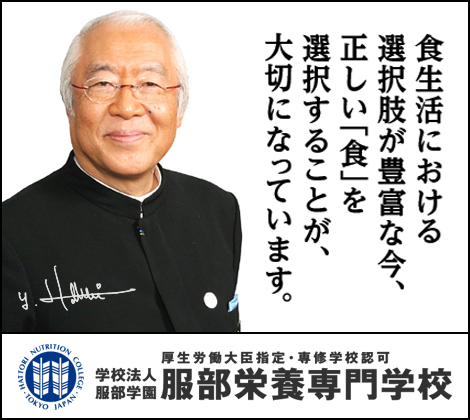2月の行事といえば、「節分」ですよね。
そして節分と言ったら「豆まき」!
そこで今回は、「豆まき」の由来や意味、あまった煎り大豆を活用したレシピについてご紹介します。
【節分とは】
節分は季節を分けるという意味があり、「立春」「立夏」「立秋」「立冬」の前日のことをいいます。
本来は年に4回あるのですが、なかでも旧暦で新年のはじまりを表す春が最も重要だったため、「立春」の前日のみを指すようになりました。
【どうして豆をまくの?】
昔は季節の節目に邪気が入りやすいと考えられていました。
それらを退治するために行うようになったのが「豆まき」です。
中国から伝わった追儺(ついな)の行事を取り入れたもので、鬼やらいともいい、この風習が日本に伝わって、平安時代の宮中行事として行われるようになりました。
鬼が嫌うイワシの頭を大豆やヒイラギの小枝に刺して、火であぶったものを門や戸口に立てたり、鬼打ち豆、節分豆と称して煎った大豆をまいて厄払いをします。
日本では昔から、米・麦・ひえ・あわ・大豆には「穀霊」が宿っていると考えられていました。
そのなかでも大豆は最も粒が大きく、まいたときの音も大きいため、鬼(邪気)を払う力も大きいと考えられていたのです。
そして魔の目(魔目=まめ)にぶつけて魔を滅する(魔滅=まめ)の語呂合わせとしての意味もあり、節分に豆まきをするようになりました。
【生の大豆ではだめ?】
大豆は必ず煎ってから使用します。
生の大豆で豆まきをし、拾い忘れて芽が出てきたら…。芽がでてくるのは縁起が悪く、災難がふりかかると言われているため、必ず煎った大豆を準備しましょう。
また、「豆を煎る」=「魔目を射る」という語呂合わせに通じるとも言われています
豆まきのために煎った大豆は「福豆」と呼ばれ、本来は升に入れて神棚に供えます。
ちなみに、「升(ます)」は、成長や発展を表す「増す」や「益す」に通じ、縁起物とされています。
【豆まきはいつするの?】
鬼は真夜中(丑寅の刻)にやってくるといわれているので、豆まきは夜に行いましょう。
家の玄関や窓を開けて、「鬼は外」と言って鬼を追い出すように豆をまき、鬼が戻ってこないように戸や窓を閉めてから「福は内」と言って部屋の中に豆をまいて福を呼び込みます。
豆まきがすんだら1年間無事に過ごせるように願いながら自分の年齢よりも1つ多く食べる「取り豆」という習慣もあります。
これは、1年の厄除けを願う意味がありますが、地域によっては「数え年として1つ多く食べる」「数え年と新年の分を加えて2つ多く食べる」「年の数だけ食べる」などさまざまなようです。
また、小さいお子さんの場合、煎り大豆は窒息や誤嚥のリスクがあるので、注意しましょう。
食べきれないときは、熱いお湯を注いで飲む「福茶」にしていただく方法もありますが、今回はご飯と一緒に炊き込んでいただきましょう!
それではレシピをご紹介します。
【煎り大豆ごはん】
<材料(2合分)> 調理時間:40分(浸水時間を除く)
精白米・・2合(300g)
煎り大豆・・70g
A酒・・小さじ2
Aほうじ茶(茶葉1gに対し350mlの湯で抽出したもの)・・350ml
塩・・小さじ1/2
<作り方>
- 精白米は洗って30分ほど浸水させ、ザルに上げて水気をきる。
- フライパンに大豆を入れ、木べらで混ぜながら煎る。
こうばしく色づいたら火を止める。 - 炊飯器の内釜に(1)・Aを入れてひと混ぜし、(2)の大豆を加えて普通に炊飯する。
- 炊けたら塩を振って混ぜる。
煎り大豆を使うことで時短になります。
また、フライパンでこうばしく煎ることで風味が増し、おいしく仕上がります。
いかがでしたか?
毎年あたり前にしていた「豆まき」。
歴史や決まりごとを知ると、次の節分が楽しめそうですね。
今年の節分は、2月2日。
ぜひ、家族みんなで「豆まき」をし、邪気を払って一年の無病息災を願いましょう。
Text by くまこ/食育インストラクター