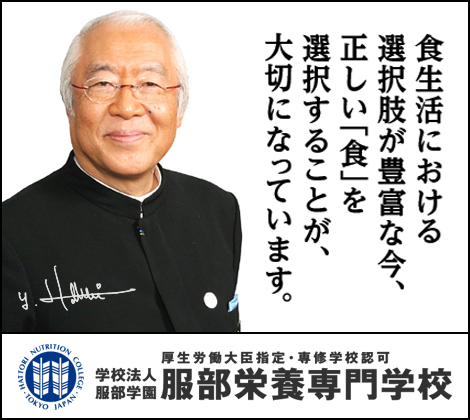子ども達は嫌いな食材があると食事が進みませんね・・・。
さまざまな食材から栄養を摂って「健康的に成長して欲しい」と思う親心はなかなか伝わらないものです。
では、どうしたら食べてくれるようになるでしょうか。
今回は食材別ではなく、食事全体としてのお話です。
【好ましい味・苦手な味】
私たちは食材の味や調味料による味付け・調理の仕方によってさまざまな味の食事をしています。
味を感じるメカニズムは、舌や上あごなどにある味を感じる「味蕾(みらい)」という細胞から、味覚神経を通って脳に情報が伝えられ、識別しています。
私たちが感じることが出来る味は「甘味」・「塩味」・「うま味」・「酸味」・「苦味」の5つで、「五味」や「基本味」と呼ばれています。
5つの味のうち、甘味・塩味・うま味は生きていく上で必要な糖分やミネラル・たんぱく質に由来するので、本能的に好ましい味と感じます。
それに対し、酸味や苦味は自然界では腐敗や毒を連想させるものの味であることから、苦手な場合が多くなります。
特に乳幼児は、味に対する経験値が少ないので、酸味や苦みに対して敏感です。
「辛味」や「えぐみ」・「渋味」は、熱さ・冷たさ同様、三叉神経を通じて伝わる「刺激」に分類されるので、味ではありませんが苦手と認識されやすくなるのです。
【好き嫌いは味だけではない?】
嫌いな理由は味だけではありません。
離乳食期の我が子を思い出してみてください。
ペーストから刻んだ状態にステップアップさせる・刻んだものをコロコロの形状にステップアップさせるといったタイミングで、今まではおいしそうに食べていた食材を「べぇ」と出したことはないでしょか。
これは、今まで経験したことのない「食感」にとまどったことによるもので、経験がないために起こります。
最初はとまどっていても、同じ状態を繰り返すことで慣れ、最終的には何事もなかったかのようにその形状を受け入れていきます。
そのほかにも「食べにくさ」や「見た目」・「トラウマ」・「お友達の影響」で嫌いとなることもあります。
【嫌いを克服するには】
食事は味だけでなく見た目や香りなどの要素も重要です。
私たちは、五感(視覚・嗅覚・触覚・味覚・聴覚)をフルに使って食事をしているので、まずは子どもが五感のうちの何に対して嫌悪感を示しているのかを探ってみましょう。
●味
食材の味が苦手なのであれば、「油で炒める」・「揚げる」・「水にさらす」・「ゆでる」・「少し味付けを濃くする」などしてみましょう。
味付けが苦手な場合は、苦手となる調味料や食材の量を調整して食べやすくしてみてください。
●食感
食感が苦手なときは、苦手食感について確認してみましょう。
「加熱が足りなくてかたい」・「加熱のし過ぎでやわらかすぎる」・「筋っぽくて噛み切りにくい」・「ヌメヌメして食べにくい」・「パサついて食べにくい」などの意見が多いです。
かたい場合はやわらかくなるようにゆでる・(肉などであれば)やわらかくなるように筋を切ったり、酵素のある食材(まいたけやパイナップル・玉ねぎなど)や水分のある調味料をもみ込むとよいでしょう。
繊維質で筋っぽい食材・皮がかたいといった場合は、長さを短くする・皮をむくなどで食べやすくなったりします。
ぬめりはゆでたり洗って落とし、パサつきはトロミをつけて飲み込みやすくすると解消します。
●見た目
見た目がNGという場合は、王道ですが「すりおろす」・「細かく刻む」などして見えなくしてしまうのがよいでしょう。
ただし、食材の細胞が壊れてしまうので、苦味やえぐみといった別の要素が出てくることがあります。
食材によって、このやり方は不向きな場合もあるという事は頭に入れておくと良いですね。
●におい
においが苦手な場合は、その香りをマスキング出来る調味料や食材を組み合わせます。
加熱によってにおいが薄れたり、好ましい香りに変わる場合もあるので炒めたり揚げたりするのも効果的です。
●食べにくさ
魚の小骨のように取り除かないと食べられない料理は嫌がられることがあります。
小さいうちはすべて大人が取ってあげてもよいですが、成長してきたらまずは自分でやらせ、出来ないところをフォローします。
●トラウマやお友達関係
その食材を食べたときに偶然具合が悪くなったなど、何かトラウマとなることがあると食べられなくなる場合があります。
アレルギーの可能性もあるので、無理強いはせず、様子をみましょう。
お友達も嫌いだからといった場合は、家族との食事のときに「おいしいよ」など声かけしながら、様子を見てください。
保育園や幼稚園に通っている場合は、先生にその旨をお伝えしておくと、フォローしてくれたりします。
【嫌いは避けてOK?】
無理に食べさせなくてよいという意見もありますが、さまざまな体験をすることは、その子の将来的な可能性を広げるのも事実です。
それは「食」も同じです。
あえて苦手な食材を育ててみる・調理してみるという体験をすることで新しい発見が生まれます。
苦手なものに挑戦し、克服出来た経験はほかのことへの意欲や自信に繋がります。
アレルギーなど、身体に問題が起こるという場合は別ですが、状況に合わせて大人が臨機応変に対応することは大切です。
しばらく間を空けてみる・何も言わずにお皿にのせてみると、意外とすんなり食べることもあります。
苦手なことをネガティブにとらえるのではなく、「パパやママも昔は苦手だったんだよ。」など、子どもの気持ちに寄り添って一緒に解決してくださいね。
苦手食材を使った料理を出すときは、子どもが好きな料理も一緒に出してあげましょう。
一度にたくさん食べさせようとするのではなく、まずは「ひとくち食べてみよう」など、小さな一歩をあと押ししてみてください。
次回は、子どもの苦手上位に来る食材の上手な取り入れ方についてご紹介しようと思います。
Text by さゆり/食育インストラクター