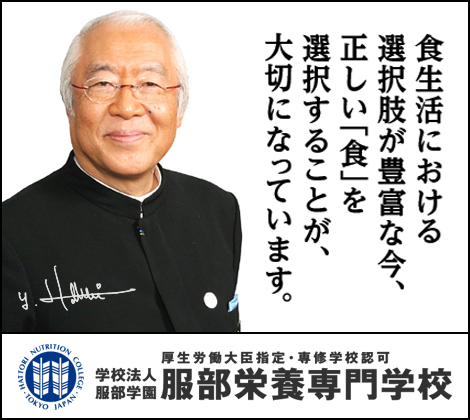おにぎりに巻いたり、佃煮にしたりと、日本人の食生活に海苔は欠かせないですよね。
今回はそんな海苔についてのお話です。
【海苔の歴史】
海苔の歴史は古く、701年に制定された日本で最初の法律である大宝律令では、税の一種として約30種類の海産物があげられており、そこに海苔も含まれていました。
その後、平安時代の制度や儀式などを記した延喜式(えんぎしき)には宮中への献上品や上級貴族への給仕のひとつとして海苔が藻類中第一等の価値があったと記されており、これは岩海苔であったといわれています。
当時の海苔は大変貴重な高級品だったため、一般の人たちの間に広まるのは江戸時代になってからです。
江戸時代になると、アマノリなどの海苔の養殖技術が確立し、現在の東京湾で海苔を養殖し、和紙の製紙技術を用いて、現在私たちが知っている四角い形に加工するようになりました。
【海苔の名前の由来】
海苔という名前の由来は、「ヌルヌルする」を意味する「ぬら」という言葉が訛ったものだといわれています。
現在「海苔」といわれて想像する四角く乾いたものではなく、収穫する際の生の状態が由来になったようです。
その後地域によって呼び名が変わり、江戸時代になって「海苔」という漢字が使われるようになりました。
【2月6日は海苔の日】
先ほどお話した通り、大宝律令により多くの海産物が租税として納められていました。
このことから、海苔は産地諸国の代表的な産物だったことがうかがえます。
この史実に基づき、大宝律令が施行された大宝2年1月1日を西暦に換算すると、702年2月6日となります。
そのため、業界の発展祈願の気持ちを込めて、2月6日を「海苔の日」に定めました。
【海苔には裏と表がある!?】
皆さんは海苔に表と裏があるのをご存じですか?
海苔をよく観察するとザラザラとした面とツルツルとした面があります。
一般的にはツルツルした面が表、ザラザラした面が裏です。
これは巻きずしやおにぎりなど、巻いたときにツヤのある面を表にする方が、見た目も口あたりもよくなるからです。
また、海苔づくりは江戸時代に開発された海苔抄き(のりすき)という製法が、現在でも使われています。
これは、和紙の製法と同じく、細断した海苔をすだれに広げて抄くというものです。
この時、すだれに接した側が裏面となり、ザラザラした見た目になります。
【海苔をおいしく保存する方法】
パリっとした食感のよさは海苔の魅力のひとつです。
でも、開封後数日経つとしなしなになってしまった経験はありませんか?
早めに食べきるのが一番ですが、どうしても使い切れずにあまってしまいますよね。
海苔は、光や温度、湿度に敏感です。
開封後は密閉機能の高い容器・保存袋に海苔と乾燥剤を入れ、しっかり空気を抜いてから冷暗所・冷蔵庫で保存しましょう。
長期保存の場合は冷凍保存がおすすめです。
冷蔵庫・冷凍庫で保存した海苔は常温に戻してから使用するようにしましょう。
袋を開けたときに室内と海苔の温度差がありすぎると、海苔が結露してしまうので、注意が必要です。
いかがでしたか?
海苔は古くから愛されてきた食材です。
2月6日の海苔の日には、ぜひおいしい海苔を食べて下さいね。
Text by あお/食育インストラクター